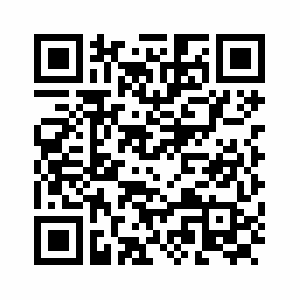- 広報ブログ
お家づくりで失敗しないために重要な「建築士」とは?
「建築士と建てる家」や「設計士による間取り提案」といった言葉、住宅会社の広告でよく目にしますよね。
しかし、実はそこに思わぬ落とし穴があることも…
そこで今日は「建築士」「設計士」「建築家」の違いを分かりやすく解説しながら、安心して家づくりを進めるためのポイントをお伝えします。
お家づくりで失敗しないために重要な「建築士」とは?
営業スタッフから設計スタッフへの“バトンタッチ”が肝心な理由
愛知県岡崎市で注文住宅を建てる際、多くの方はまずハウスメーカーや工務店の営業スタッフと打ち合わせを始めます。
しかし、契約後に担当が「営業」から「設計」に変わる流れが多いことをご存知でしょうか?
この営業→設計の引き継ぎこそが、家づくりの満足度を左右する大事なポイントです。
営業スタッフと設計スタッフの違い
一般的に、営業スタッフは建築士の資格を持っていない場合がほとんどです。
そのため、最初に作られる間取りが、実際の建築基準や構造に合わず、後から大きく修正されるケースも珍しくありません。
岡崎市でもよくあるのが、
•建築基準法の制約で間取りが変わってしまう
•夏の日射を考慮していない窓配置
•冬の冷え込みに対応できない断熱仕様
といった、法律や地域の気候に合わないプランです。

「設計士」と「建築士」は別物
設計士という肩書きは資格がなくても名乗れます。
一方で、建築士は国家資格であり、一級・二級・木造の3種類があります。
もちろん資格がなくても経験豊富な設計士さんは存在しますが、初めて会ったときにその実力を見抜くのは困難です。
大切な家づくりは、一級建築士・二級建築士などの資格を持つ「建築士」と進める方が、構造・断熱・耐震などの専門的な配慮が行き届きます。
特に、岡崎市のように夏と冬の気温差が大きい地域では、特に断熱・日射・通風の設計知識が不可欠です。
そのため、名刺やホームページで「建築士資格の有無」を確認することが安心への第一歩です。
建築家と建てる家の「理想と現実」
建築家という言葉は非常に曖昧で、建築家=一級建築士という意味ではありません。
でも建築家と聞くと、なんとなくデザイン性の高い建物を設計する人というイメージがありますね。
最近は「建築家と建てる家」というキャッチコピーも増えていますが、「建築家と建てる家」と聞くと、完全オーダーメイドで理想が叶うイメージがあります。
しかし、その建築家が社外のフリーランスや業務委託だった場合…
•打ち合わせはオンラインのみ
•回数が限定される
•現地調査や日常の細かい相談ができない
というケースも多く、結果として生活にフィットしない家ができてしまうことも。

安心して任せられる設計パートナーの選び方
•1.建築士資格の有無を確認する(一級・二級)
•2.実際の設計事例を見せてもらう
•3.打ち合わせ回数や形式を事前に確認する
これらをクリアしている会社であれば、営業と設計の連携もスムーズで、希望通りの家が実現しやすくなります。
また、地域に根差した工務店を選ぶことにより、地域の気候や土地条件、法令などへの理解がある可能性が高くなります。
私たちは岡崎市で数多くの住宅を手がけてきた建築士として、高気密・高断熱・回遊動線・家事ラク間取りの家をご提案しています。
ぜひ一度、直接ご相談ください。